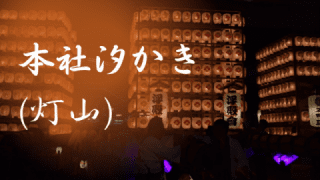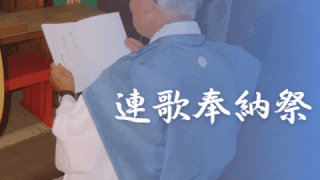宇原神社神幸祭

宇原神社神幸祭は、「国家安全」・「五穀豊穣」・「萬物平安」を祈り、嘉吉二年(西暦一四四二年)より五百有余年にわたり続く例大祭の神事です。9月下旬から10月上旬に鉦卸し、連歌奉納祭、本社汐かき、例祭、山笠汐かき、神幸祭、当場渡しの順序で行われます。
神幸祭当日、宇原神社の御神輿が神幸場即ち旧宮所の浮殿の地(石塚山古墳の前、現在苅田町役場前広場)に御行幸されます。
一方、氏子14区が御神輿の供として、思い思いの意匠を凝らした飾り山笠を引き神事場に勢揃いする。この「かんだ山笠」は県指定無形民俗文化財に指定されています。
神幸祭次第
08:30 出御祭
09:00 出発
10:00 到着
10:15 着御祭
14:30 還幸祭
15:00 出発
16:00 本社到着
16:05 着御祭
内容
祭当日午前9時頃、神職、氏子総代、神輿かき(氏子青年会)、御供人、鉾持ちなどが神社に集い祭典(出御祭)執行の後、神輿発輦所定の従者は所定の服装をして次の順序でついていく。
①塩湯祓②獅子頭③神職④社名旗⑤五色旗⑥辛櫃⑦太鼓楽人⑧剣鉾⑨太刀持⑩鋏箱⑪賽銭箱⑫巫女⑬祓串⑭御神輿⑮宮司⑯大傘⑰神職⑱氏子会長⑲総代⑳鉾持ち㉑殿
御神輿は楽の奏せられる中を厳粛にしづしづと宇原神社から御旅所へ向かって行幸される。その途中宇原神社御祭神に由緒ある「磯の上」の休憩所で少時御休憩なされる。それから御出発なされ、11時頃御旅所に御到着され、安置される。
この時から参拝者は踵を接して続々参拝する。
一方、氏子の各区では、御神輿の御供をするため飾り山笠(岩山)を出す。昼には御神輿の前に14基の山笠が勢揃いする。
神幸祭の当日午前2時頃から当場の人々は各区の山車の置いてある所(格納庫)に集まり、前日の幟山に使った山車に飾り付けを始める。山笠は合戦記や物語をテーマに巨大な岩や人形を飾った豪華かつ華麗な飾り山へと再び様変わりする。竹骨に着色紙張りの岩や波や美麗な御殿を飾り付け、五色の紙すだれを付け、人形数体を飾って演劇の場面を現出し、ホテ花を付け、山笠の胴体に色とりどりの幔幕を張る。この山笠は高さ10米、幅3米位のものである。
10時頃山笠は大人がつき子どもに引かれ神事場へ向かう。各区の人々は各区規定のマークを背に染めつけた法被を着用し、区毎の色鉢巻きをしめ、これに従っていく。当初からの慣習に従い、まず集区の山笠が出発して御神輿を迎えに行き、その先導をして御旅所に行く。それから協議の上決められた順番で南北両郷とも鉦太鼓を威勢良く打ち鳴らしながら神事場に行き、山笠14基は規定の順列に並び、その業を競う。
この時より、町内外の参拝者万余が集まり、多数の出店も出て雑踏を極め、賑やかな苅田神事の絵巻を繰り広げるのである。
神幸守(じんこうまもり)
鉾持ち神事(ほこもちしんじ)
苅田山笠
宇原神社神幸祭に御神輿の供として、氏子14区が思い思いの意匠を凝らした飾り山笠が出されます。
この「かんだ山笠」は、昭和51年4月24日に福岡県無形民俗文化財に指定されました。